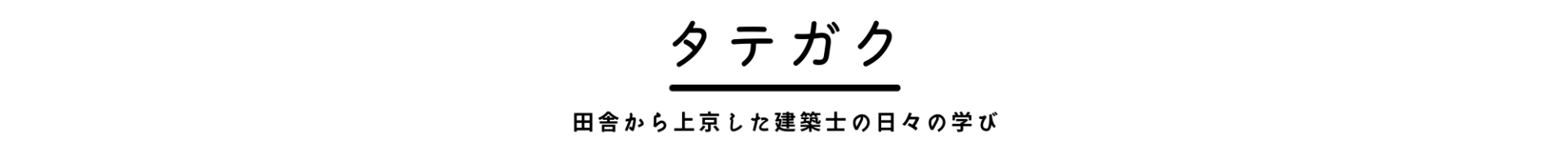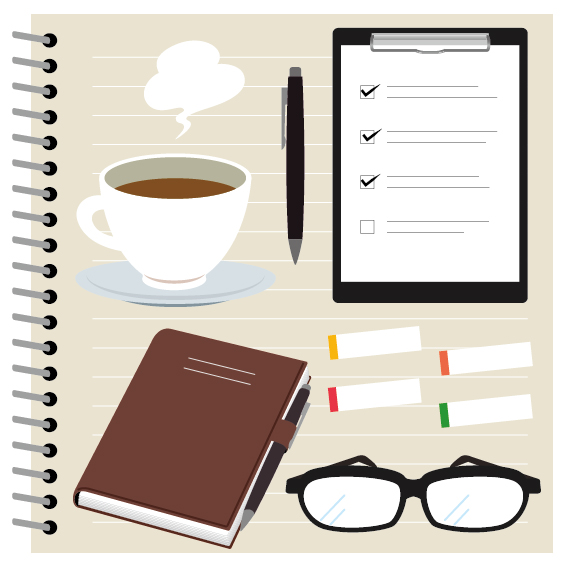
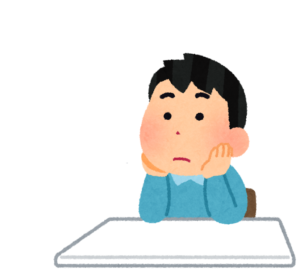
「一級建築士試験の勉強をいつから始めたら良いのか知りたい。とりあえず一級建築士の免許が欲しいけど、果たしていつから勉強すれば良いんだろう?いつから始めるか決め方ってありますか。」
本記事ではこういった学習者向け。
こんにちは。ポンタです。
僕はアトリエ系の構造設計事務所に3年ほど勤めてまして、令和元年度の一級建築士試験で学科、製図共にストレート合格しました。
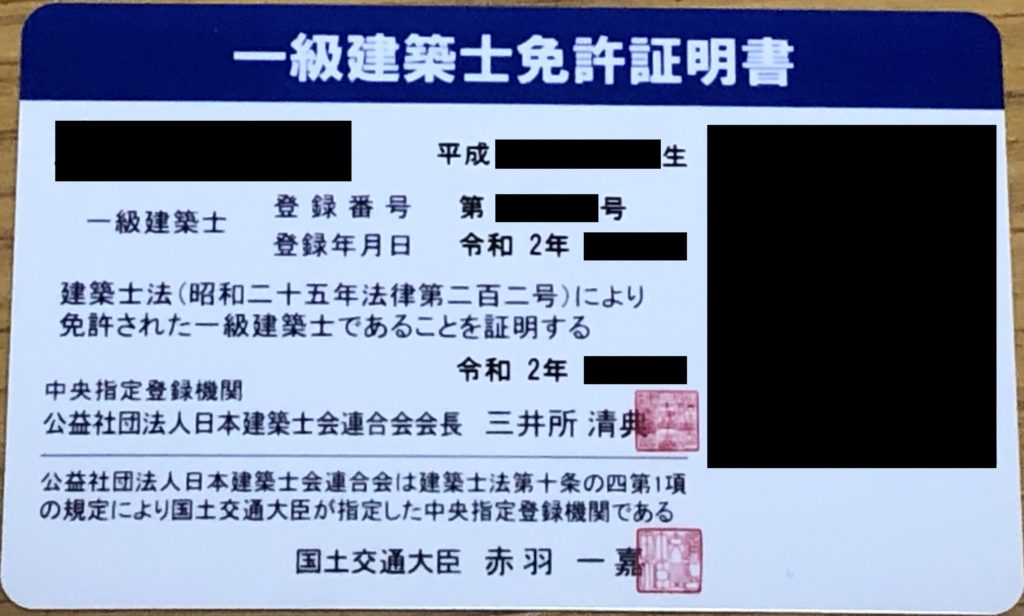
ちなみにこれが一級建築士の免許証です。シンプルなデザインですね。真っ黒で分かりづらいですが令和2年の登録になっています。
よくある悩みなんですが「一級建築士の勉強はいつから始めればいいの?」という問いがあります。
僕が思うに「特に決めていなければ11月に始めるのがベスト」だと思います。基礎から始める時間もありますし、自分のペースで学習スケジュールを組めるからです。
そんなわけで今回は「一級建築士の勉強をいつから始めるか」について紹介していこうと思います。
一級建築士の勉強はいつから始める?「11月」がベストです

とりあえずは、11月から始めればOKだと思います。
11月からであれば、「ある程度早めかな・・・」という感じですね。
11月がベストである根拠とは
本試験が7月なので、11月から始めると「基礎から」じっくり学ぶ余裕があります。
- 11〜12月:準備+基礎固め
- 1〜3月:基礎固め+範囲網羅
- 4〜5月:弱点克服
- 6〜7月:最後の追い込み
だいたい上記のイメージです。7月の本試験までに十分対策する時間はあるかな、という印象です。
※勉強を始める期間が遅くても巻き返すチャンスはありますので、詳しくは後述します。
資格学校が11月から始まる
ちょうど10月に前年の製図試験が終わるため、新年度のコースが開講されます。
ぶっちゃけ一級建築士の勉強ってかなり大変でして、独学も不可能ではないんですが、かなり大変ですし運の要素にも左右されます。
僕も受験生時代は、講師の方に質問する機会があったのですが、「講師の方達の説明は分かりやすいなぁ」と感じました。
なので、勉強していてどうしても分からないとこはすぐに聞くことができますし、そこに悩んで限られた勉強時間を浪費する事も減ります。
資格学校に通えば、周囲の環境や最新の情報なども入ってきますし、モチベーションも高まるでしょう。
ただそれなりにお金はかかりまして、このお金を「高い or 安い」と考えるのは人それぞれですね。
もし資格学校がどんなものか気になる方はこちらから無料で資料請求できます。
上記はTACという資格学校で、料金は真ん中くらいの資格学校となっています。感覚を知るためにはちょうど良いかと。
4月には一通りの科目に触れられるくらいです
11月から勉強を始めれば、4月には一通りの科目に触れられるくらいは到達できるかなと思います。
4月までに一通りの科目に触れられていると、弱点克服の時間が取れます。4、5月のゴールデンウィークで徹底的に弱点を補完できますね
なお、僕の場合は4月の段階で問題集2周行くか行かないかくらいはできており、時間の取れている人になると、3周はしていました。なので、11月から勉強を始めると、ゴールデンウィークを苦手対策に使うことができ、合格に一気に近づくと思います。
こういった余裕を持つには、早い段階で一通りの科目に触れている必要があり、一つの目安として「11月くらいに勉強を始めましょう」ということですね。
言うまでもないですが、僕は一級建築士の勉強に時間を費やして後悔はないです。
一級建築士の勉強時間に900時間ほど使いましたが、ストレートで合格することができましたので、自信になっています。
いつから勉強するかに、こだわり過ぎる必要はないです

11月から勉強を始めようと言いましたが、じゃあそれ以降に勉強を始めたら遅いのかと言ったら、答えはNOです。もちろん、早く始めた人より進捗はおそくなりますが学科試験の合格も可能です。
結論:常に本試験を意識した勉強をする
例えば、4月から勉強を始めた方とします。
やはり、細かいところまで対策しようとすると7月の学科試験まで間に合いません。言い換えると、「出題頻度の高い単元と習得時間を意識することでコスパ良く勉強できる」と言うことです。
これは過去問の問題集を見てもらえればわかるんですが、単元によって出題の傾向があります。
問題の出題頻度例
- 毎年必ず出題されコスパの良い問題:消防法、建築士法、、、
- 数年に一度出題されるかも知れない問題:住宅品質確保法、、、
法規の場合、消防法は毎年1問出題されているのに対して、住宅品質確保法は過去10年で2問しか出題されていません。
※令和元年度時です。
つまり、「勉強したことがどれくらい点数に結びつくかを意識する」ことが必須ということです。
短期講座を活用しよう
資格学校には4月や5月に開講している短期集中講座があります。
ぶっちゃけ時間に余裕もないので短期講座に申し込むのもありです。
自分なりにどう勉強するかイメージが持てている人はいいのですが、この辺の講座は点数に直結するところをあらかじめ教材としてくれていますので問題を解くことだけに集中できます。
長期講座より価格は安いので迷っているのであれば、申し込んでみるのも一つの方法です。
どちらにしても、「もう勉強始めるのは遅いかも、、、」と迷っている時間はもったいないです。短期間でも方法によっては合格の可能性もあります。なんにせよ、まずは挑戦してみる事です。すぐに勉強を始めましょう!
一級建築士の勉強を始めた後のことを想像しよう【自分のペースを考えてみよう】

ここまで読んで、「よし、11月、または直ぐに勉強を始めようかな」と思った方は、素晴らしい状態です。
しかし、厳しい意見ですが、「勉強している=ゴール」ではないです。
当たり前ですが、「勉強している=スタート地点」です。
一級建築士の勉強を始めた後とは
結論としては、「自分の勉強ペースが見えてくる」という事です。
これは実際にやってみないと難しいですが、例えば次のような例で考えてみます。
例:帰宅後どちらの行動が選ばれやすいですか。
- 疲れているけど少しでも勉強してから寝よう
- 明日も仕事だし休日に巻き返そう。
この例で言えば選ばれる可能性が高いのは「圧倒的に後者」だと思います。
その理由は、人間は本能的に「楽な方」や「嫌なことは避ける」と考えがちだからです。
誰もが思っていることですが、毎日コツコツ勉強するほうが成績は伸びます。
しかし、仕事で疲れている事もあり、どうしても後回しになってしまう場合もあります。
勉強を始めたら、自分のペースを分析しよう
1ヶ月も勉強してみると、「自分の勉強のペース」が見えてくると思います。
おそらくですが、事前に立てた勉強スケジュール通りには進まないなぁ・・・みたいな状態になると思います。
僕も実際にそうでした。
そこでやるべきことは、「自分のペースに合わせてスケジュールを調整する」ことです。具体的には、次の手順です。
- 自分の立てた勉強スケジュールを確認する
- なぜ予定通りに進まなかったか考えて、自分にあった調整をする
- 自分のペースに沿って、勉強できるであろうスケジュールを立てる
こんな感じでです。
おそらく何度も繰り返すことになりますが、結構簡単にできる作業だと思います。
具体例:週に20時間勉強する計画を立てた場合
ちょっと具体例で説明します。
例えば、「週に20時間勉強する計画を立てて、実際は15時間しか勉強できなかった」みたいな結果だったとします。
じゃあなんで時間が確保できなかったかというと、「帰宅後疲れて寝てしまったり、休日に予定があったり」した可能性が高いです。
じゃあなぜ、どうすれば計画どうりにできるのかを考えます。これは実際に勉強してみたから分かることで計画を立てた段階ではわからなかったことです。
例えばですが、「自分の生活を見つめ直して活用できそうな時間を考える、来週は仕事が落ち着くので余裕がある」などで不足分を補う事ができますね。
自分のペースを分析して、自分なりにスケジュール調整を行い、勉強していく、という事を繰り返す事で計画倒れせず、長期的に勉強を続けられると思います。
まとめ:一級建築士の勉強をはじめるなら、とりあえず11月からスタートです

記事のポイントをまとめます。
- 一級建築士の勉強始めるなら、とりあえず11月くらいから始めましょう
- 11月くらいから勉強すれば、「余裕をもって勉強」ができます
- しかしながら、いつから勉強を始めるかにこだわりすぎる必要もないです
- 短期間でも合格の可能性があり、すぐに勉強を始めるべし
- 勉強を始めたら、自分のペースを分析し、自分のあった計画を練っていきましょう
こんな感じです。要するに、自分のペース、試験の傾向を分析しながら勉強を進めていきましょう、ということです。
とりあえず、11月くらいから勉強をスタートしましょう!
また、勉強方法に迷っている方で資格学校に通う費用や、時間がないなら【スタディング】がオススメです。
大手資格学校の1/10以下の費用で受講できて、動画を用いた通信講座なので「自分のペースで勉強」できます。
なお、一級建築士の学科試験の勉強方法については以下の記事で詳しく解説しています。
-

-
【一級建築士】学科試験の勉強法でお困りですか?【初学者向けに僕が合格した方法を紹介!】
続きを見る
というわけで以上です。
皆さん多忙な中、勉強するのは大変でしょうけどがんばって下さい。
本記事が少しでもみなさんの役に立ててれば幸いです。