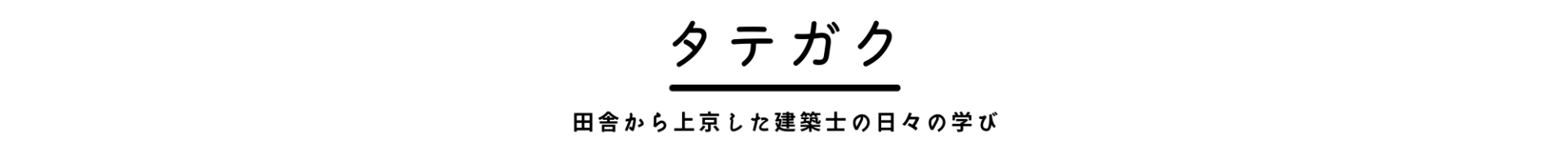-

-
【一級建築士】試験内容について【学科試験の解き方解説】
こんにちは。ポンタです。 本記事ではこういった学習者向け。 今回は一級建築士の試験内容と僕が実際に行っていた問題の解き方について説明していきます。 ちなみに僕はアトリエ系の構造設計事務所に3年ほど勤め ...
-

-
【一級建築士】計画の勉強法【得点につながる項目紹介】
計画のポイントは「暗記がメイン、時間をかけ過ぎない、他の科目と関連付ける」です。暗記すればした分が点数につながるので、得意科目にしましょう。
-

-
【一級建築士】法規の勉強法【得点につながる項目紹介】
法規のポイントは「法令集は何より優先、大小関係に注意する、暗記で時短」です。法令集は便利ですが、頼りすぎると時間が足りなくなります。目標は、法令集を引かずに解けるようになりましょう。
-

-
【一級建築士】施工の勉強法【得点につながる項目紹介】
施工のポイントは「数値や語句をひたすら暗記、写真や図で理解、初出題の対策必須」です。施工は他の科目に比べて初出題の問題が多いです。過去問だけでのカバーは難しいです。対策として、テキストや施工管理技士の問題でまだ出題されいない部分を勉強することが重要です。
-

-
【一級建築士】1日の勉強スケジュール【学科編】
こんにちは。ポンタです。 本記事ではこういった学習者向け。 僕が実際にどうやって勉強したのかその方法を紹介していきます。 ちなみに僕はアトリエ系の構造設計事務所に3年ほど勤めてまして、令和元年度の一級 ...
-

-
新卒で建築会社を辞めてもなんとかなります【現場仕事は向かなかった】
僕の答えは苦しいのであれば新卒でも辞めた方がいいです。「不満がある状況だと受け身になりがちで、同じ時間、働くとしても上達が遅くなります。」自分から能動的にできる事をした方がいいと思います。
-

-
【一級建築士】構造の勉強法【得点につながる項目紹介】
構造のポイントは「絵に書いて暗記、力学は早めに対策、大小の影響に注目」です。構造は用語が分かりにくく、字面で理解しようとすると大変です。絵や図にして覚えると分かりやすいです。また、部材や比などが大小することの影響を理解することも問題を解くポイントです。
-

-
【一級建築士】学科試験の勉強法でお困りですか?【初学者向けに僕が合格した方法を紹介!】
一級建築士の学科試験の勉強法で悩んでいますか?この記事では一級建築士の学科試験の勉強法について解説しています。実際に僕が一級建築士試験に合格した経験をもとに記事を執筆しています。
-

-
【一級建築士】環境・設備の勉強法【得点につながる項目紹介】
環境・設備のポイントは「式の意味を理解する、環境工学は早めに着手する、設備は製図試験を意識する」です。設備の知識は製図試験でも特に重要な知識です。特に空調設備、給排水設備は学科で必ず理解しておきましょう。
-

-
一級建築士の勉強する順番はこれ!【優柔不断な人に読んでほしい】
「習得にかかる時間と出題頻度によって勉強する順番を決める」です。科目や項目によって必要な時間は変わってきます。勉強する順番を決める事で効率の良いスケジュールを組めると思います。